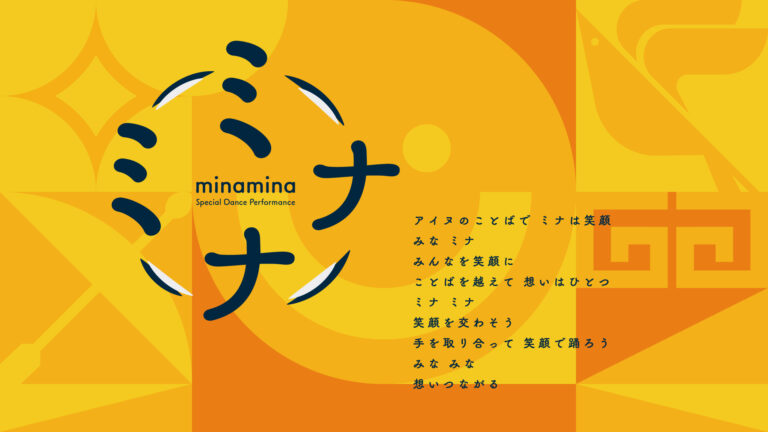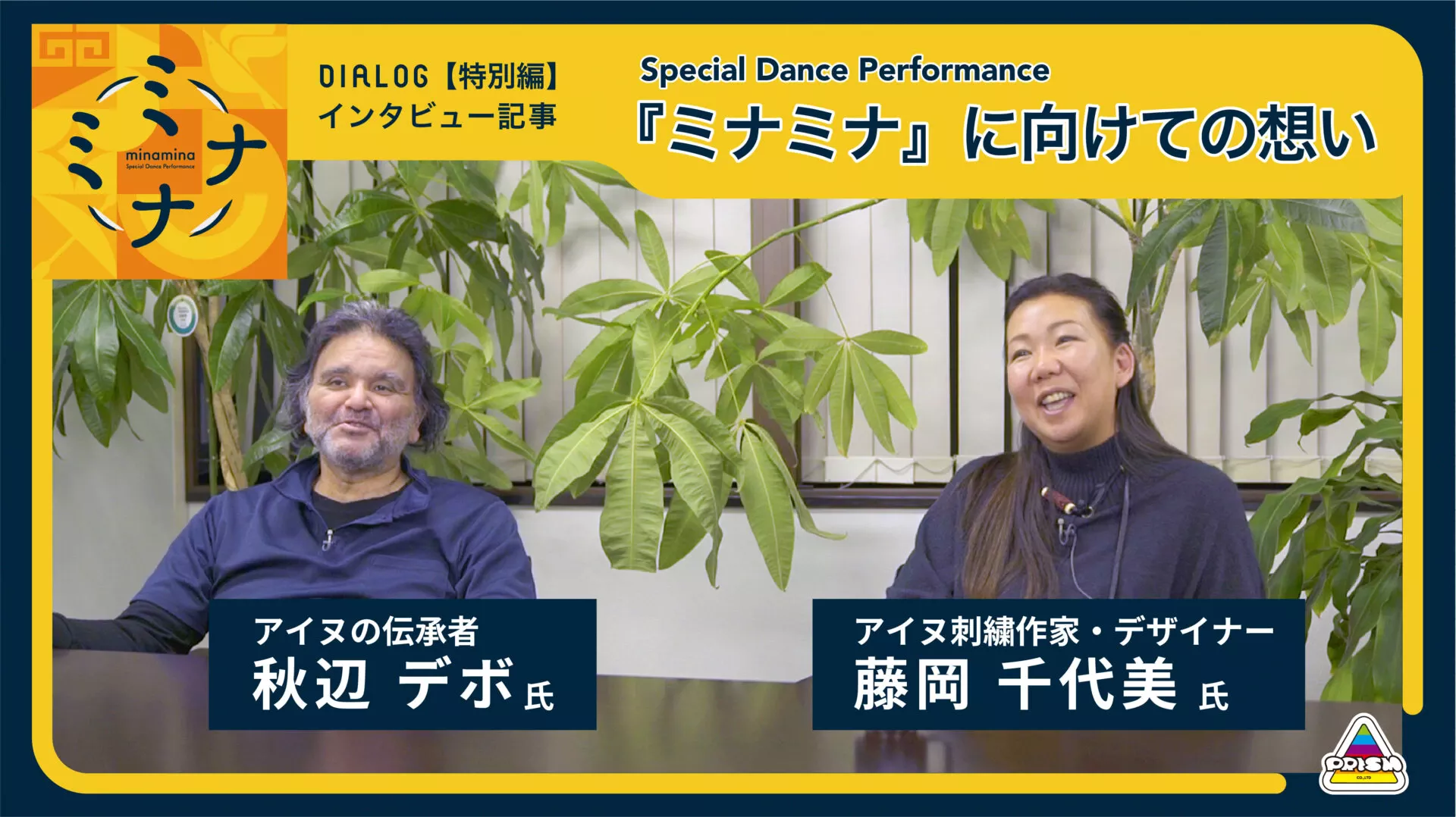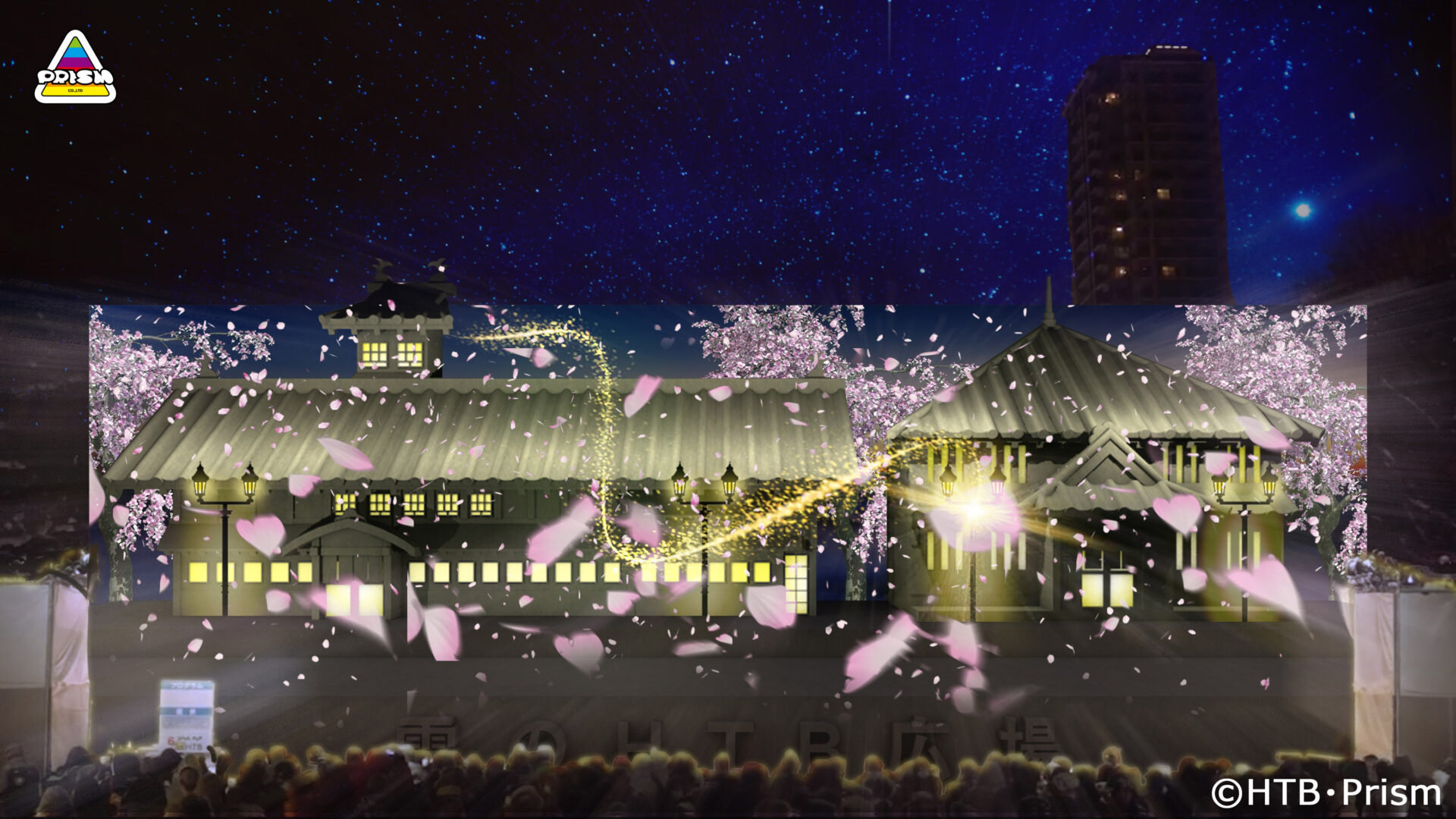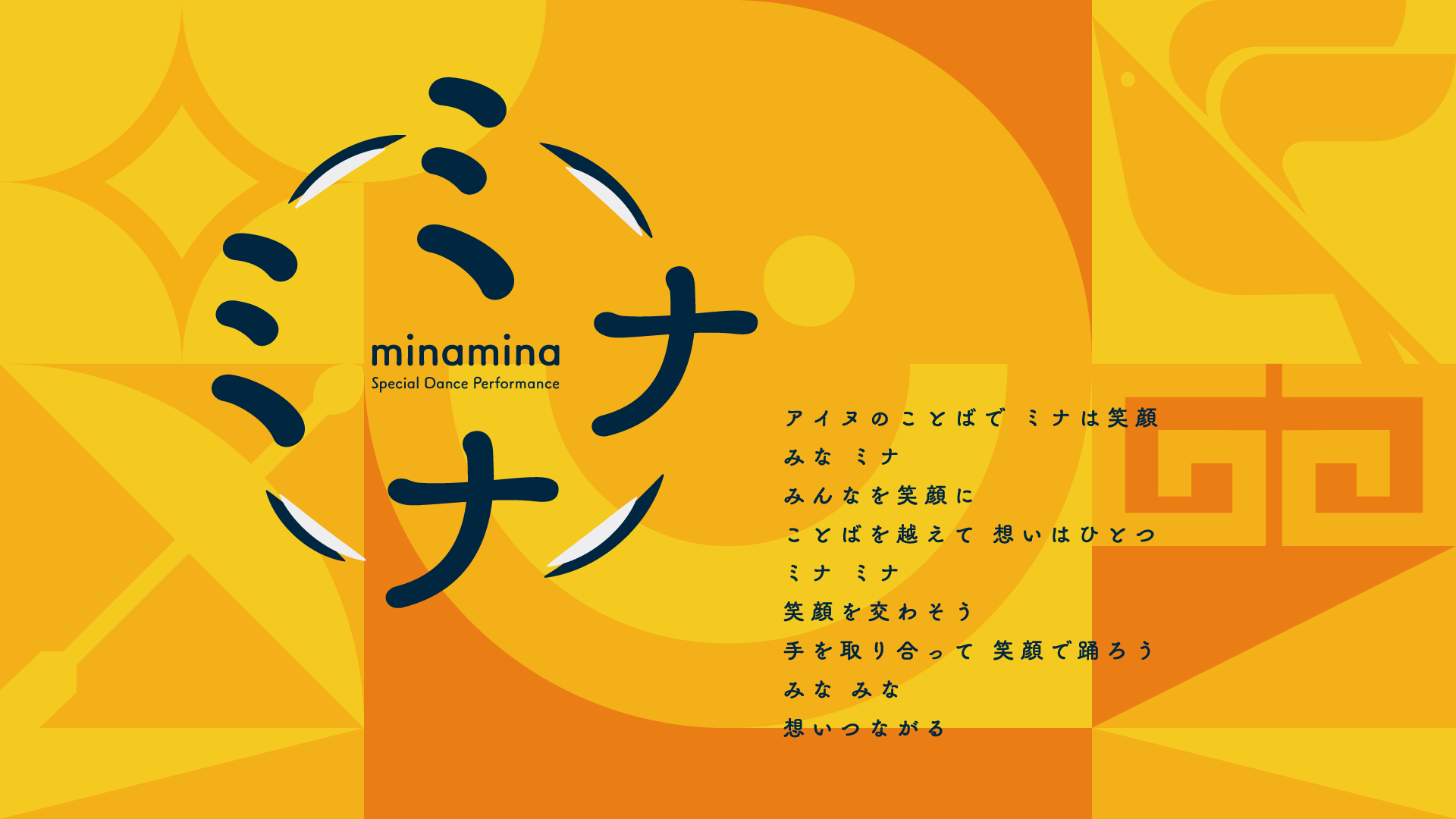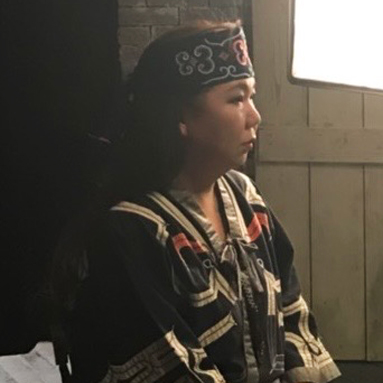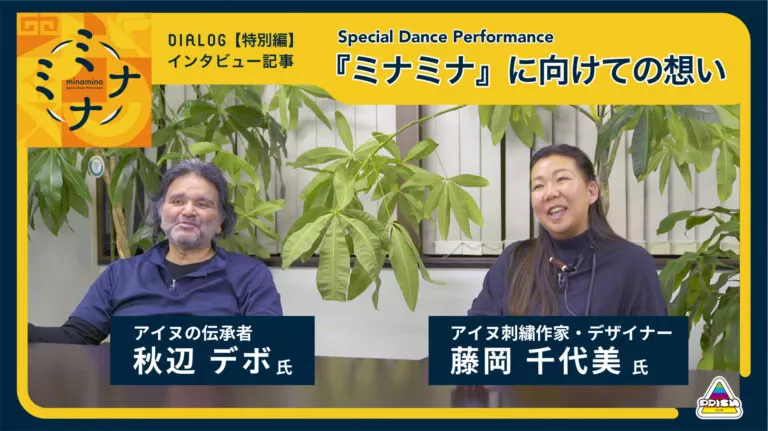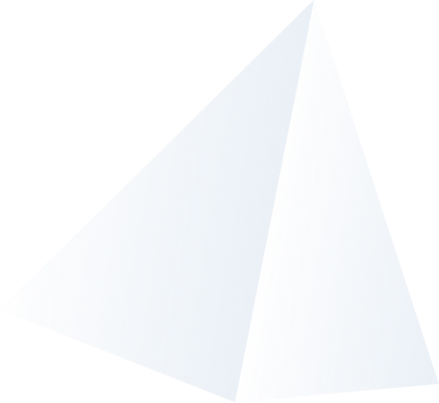
-
2024.05.02
-
2023.12.19
-
2023.09.14
-
2022.12.02
-
2022.09.22